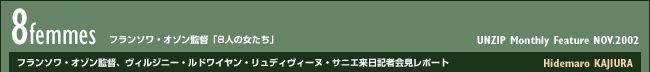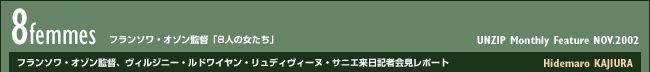ヴィルジニー・ルドワイヤンさん、リュディヴィーヌ・サニエさんからも一言ずついただけますか?
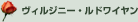
「こんばんわ、本当に多くの方々にこの記者会見に来ていただきましてありがとうございました。まあ『8人の女たち』を演じるというのは、私にとって非常に有効な、とても素晴らしい経験になりました。とても私は好きな映画です。皆さんに気に入ってもらえればと思います」
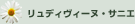
「モシモシィコンバンワ(日本語で。記者席に笑い)。私はこちらに伺うことができて大変幸福に感じております。日本に来るのも東京も初めてですけれども、この映画を紹介するためにこうして日本にこれて、大変光栄に思っております」

ありがとうございました。それでは質疑応答とさせていただきます。
Q1:ヴィルジニー・ルドワイヤンさんに。来年はぜひ横浜フランス映画祭に来ていただきたいと思っております。次の映画のプロジェクトについてですが、エリック・ロシャン監督の映画でマリー・ジランさんと共演されると伺っていますが……。
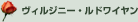
「本当は『8人の女たち』の話をできればと思っていたのですけれども。横浜映画祭の方にもぜひ行きたいと思っております。おっしゃっているプロジェクトについてですが、まだ実現化はされていません。マリー・ジランさんと共演するかどうかも、まだ決まっていません。私の一番最近の最新作というのは、ジャン=ポール・ラプノー監督の『ボン・ヴォヤージュBon
voyage』(共演はイザベル・アジャーニ)という作品になります。
Q2:監督に。今や俳優さんが一緒に仕事したい監督No.1と言われるオゾン監督ですが、そういった中で御自身の作品に起用される女優をどういった基準で選び出したのでしょうか? そして女優のお二人には、オゾン監督に起用されたことをどう思っていらっしゃいますか?
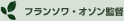
「まず、女優さんと仕事をする時は、『こういう女優さんと』とか、『ああいう女優さんと仕事をしたい』というようなことはありません。まずは役作りが一番大切でして、どういう役を自分の作品の中で作っていくか? なんです。そしてその役に一番合った人を選ぶようにしています。今回の『8人の女たち』に関しましては、初めはこんなにたくさんの大スター達と仕事をするとは考えておりませんでした。が、前作の『まぼろし』で、シャーロット・ランプリングと仕事をして非常にうまくいったので、またいい女優と仕事したいなと思いまして、女性が出てくる作品を作ったわけです。本作に関しましては、ま、お芝居のような作品にしたわけなんですけれども、3つチョイス(選択肢)がありまして、ひとつは全く知られていない女優を使う、あるは非常によく知られているスターを使う、あるいは男性を女装させて使う(笑)、という方法があったわけなんですけれども、その中では一番よく知られている女優を使うのがいいのではないかと思いまして、こういう選択となったのです。女優を選ぶにあたっては、といいますかそれぞれの役に合った女優を選ぶにあたっては、それぞれのいろいろな世代を現わしていきたい、と思いましていろんな世代の女優を入れておりますし、それから全体としては、その女優達が本当に“家族”の役割をするわけなので、女優達の間で家族を表現していきたいと思って、最も家族にふさわしい女優達を選んでいますし、また“(フランス)映画界”というファミリーを代表するような人達を選んでいます」
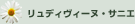
「私はフランソワ・オゾン監督と仕事をすることができ、そしてこの作品に参加することができて、非常に光栄に思っていますし、誇りに思っています。他の女優さん達に比べて私の方が少し進んでいた(有利だった)のは、私は過去にオゾン監督の作品に出ていたということですね。『焼け石に水』という作品ですけれども、この作品は『8人の女たち』とは全く違う世界の作品だったんですが、やはり同じように非常に芝居がかった、そういう(演劇的)世界として描かれたものでした。そういう経緯もあって、私はオゾン監督の仕事の仕方も大変よく心得ておりますし、彼と仕事をするのは私も非常に嬉しく、とても気持ちよく仕事のできる人だと感じています。というのは、オゾン監督は女優達の声に耳を傾けてくれますし、非常にクリエイティヴなものを持っていますし、また非常に正確です、監督はカメラも持てる人なのでフレームワークもきちんと把握していますから。そういう意味でも非常に信頼がおけるし、そしてまた大変ユーモアのある人なので、仕事をしていて楽しいんです」
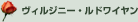
「私は初めてフランソワ・オゾン監督と仕事をしたわけなんですけれども、ずいぶん前から一緒に仕事をしたいと思っていました。オゾン監督と仕事をするというのは、女優としてとてもやり易いんです。というのは、彼はいろいろなことをすごくはっきりと、明らかにしてくれるという能力を持っていまして、特に今回は8人の女優達が一緒に存在している中で、自分の存在感というものを出していく、ということは女優にとって非常に難しいことなのですが、オゾン監督の手にかかると、とてもノーマルに、とてもシンプルに事が進むので、そういうことができる人なので、私も本当に信頼して仕事をすることができました。またリュディヴィーヌも言ってましたが、彼はカメラ映像をみてフレームを自分で作ることができる人なので、一人一人を、『こういう動きをして』と細やかな演技指導をして動かすことができるので、それだけに女優としてはやりやすい人でした」
Q3:オゾン監督に。錚々たるフランスを代表する女優さんを使ってられるわけですけれども、8人をいっぺんにこういうカタチで使われて、一番苦労された点、あるいは一番気を遣われた点、あるいは難しかった点などを教えていただければと思います。
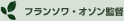
「実はですね、最初キャスティングする時には、まさか8人が全員OKしてくれるとは思っていませんでした。2、3人集まればいいかなぁと思っていたところが、8人がOKという答えが出て来てしまって。映画を作ることに関しましても、非常に早いスピードで撮影に入ってしまったんです。それまでは無邪気に、あんまり深く考えずにいたんですけれども。準備の段階では、女優さん一人一人に向き合って、一人ずつ個別に対応していたので、それで歌とか衣装、役柄についてとかをお話して、で、撮影初日に6人が集まった時にようやく『これはちょっと大変なことだ』と感じて、一緒に全員の演技指導しなくちゃいけないという現実に行き当たったわけなんです。それはまるで自分を8つに分けて、一つずつの部分を一人ずつの女優さんに与えるという感じでして……。というのは、やはり女優さん一人一人が仕事の仕方が違いますし、また要求が違うので、それぞれに適応していく必要があるんですね。ですからこれは最初の段階では『これはもう自分には無理では無いか?』とまで思ったんですけれども、女優さんの方でもですね、これはさすがに監督の方にとっては大変なことだとわかってくださいまして、いろいろ助けて下さいまして、そしてまただんだん時間が経つにつれて、うまくこうスムーズにいくようになりました」
Q4:監督に二つ質問があります。まず共同脚本のマリナ・デ・ヴァンについて。彼女は監督の初期の作品では女優として活躍していましたけれど、ここ最近の3作では共同脚本として参加されています。その関係はフランソワ・トリュフォーとシュザンヌ・シフマンの関係を想起させるんですが、監督にとって彼女はどのような存在なのでしょうか? また今回の映画の中で振り付けを担当されているセバンスチャン・シャルルも、確か監督の初期作品で俳優をされていたと思うのですが、彼とのコラボレーションのいきさつなども教えていただけませんか?
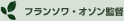
「まず最初の質問。マリナ・デ・ヴァンは、FEMIS(フランス国立映画学校)という映画学校の同級生で、彼女は監督部門にいて、卒業制作の作品でも自分自身で出演しているんですけれども、どの作品かは忘れたんですが、彼女の映画を観てとても気に入ったので、それで一緒に仕事をしようということになったんです。それで私の『海を見る』という作品に出ていただいています。その後、『ホームドラマ』にも出演していただきました。ま、彼女自身はあんまりクラシカルな正統派の脚本家というのでは無くて、一緒にプロジェクトをしながら、いろいろ細かい点を調整してくれたりとか、さらに書き進むにあたって登場人物の人物像を深めるといった所で彼女は貢献してくれています。例えば本作ではエマニュエル・べアールが演じている女中さんの役なんですけれども、元々の戯曲の中では全然面白くない役なんですね、フランスによくあるタイプの、ちょっと横柄な女中さんって感じなんですが、それがもっと邪悪なものを内に秘めている、ジャン・ジュネ(戯曲『女中たち』1947初出)の女中像とか、ルイス・ブニュエルの『小間使の日記』(63)、これは元々ミルボーの小説を映画化したものですけれども、そういう女中さんのイメージに近付けるような、そしてまた女主人とSM的な関係を持つような人物像を作り上げるにあたっては、彼女が非常に貢献してくれて、まあ二人で考えて、キャラクターづくりをしたんです。それからセバンスチャン・シャルルについてですが、彼は『サマードレス』に出てもらった時に俳優として最初に彼を知ることになって、今回の振り付けに関しては、シーラの「ボンボン」という歌の振り付けを担当してもらったんですが。振り付けはプロの振り付け師には頼みたくなかったんですね。どっちかっていうと職人風な、誰でも真似できるような振り付けにしたかったものですから。彼は『サマードレス』の後、『焼け石に水』でも仕事を一緒にしていまして、で今回も一緒にすることになったんですが、プロの振り付け師に頼んでしまうと、みんながフレッド・アステア風に踊ってしまうのもマズイと思いましたし、本人達も女優であって踊りのプロではありませんので、簡単な振り付けで、かつ観ている人もまるでTVの前で真似できるような振り付けにしたいということでセバスチャンと一緒に仕事をすることになって。面白くてかつ複雑じゃなくてセクシーなものを、ということでお願いをしたのです。で、この映画が終わった後なんですけれども、セバスチャンはそれまでは俳優だったんですが、振り付け師としての仕事がドシドシ来るようになったそうです(笑)」
Q5:まずオゾン監督に。この映画でダグラス・サーク監督の50年代のメロドラマを思わせる設定と、ディオールのニュールック、そしてさらにそこでミュージカルをさせるというなかなか、奇想天外というと言い過ぎかもしれませんが、そういうユニークなアイデアをどこから思い付かれたんでしょうか? それからルドワイヤンさんとサニエさんに。ディオール風の、それもハリウッド女優を思わせる、サニエさんはたぶん『巴里のアメリカ人』のレスリー・キャロンのイメージで、ルドワイヤンさんはオードリー・ヘップバーン風のイメージだとお聞きしているんですが、そうした大女優のイメージのある役柄を演じるというのは、いかがだったのでしょうか?
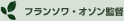
「私は自分の中にある子供的感覚っていうのを、この映画の中で蘇らせたい、と思ったのが一つありますし、それから映画が大変好きなので、その中でもとても好きな部分をこの映画の中で全面的に見せてゆきたいと思ったんですね。最初、推理小説風コメディとミュージカルをくっつけるというのは非常に実験的な試みだったんですけれども、そういうのをまずやりたいというのがありました。それから50年代のファッション、ディオールのニュールックというのは、私はファッションの中でも一番女性を美しく見せる、特に女性の体を美しく見せるものだと思うんですね。特にこの映画の中では女性達は意地悪だったりするわけですので、せめて美しくグラマラスでいて欲しいということで、そういうファッションを選んでいます。またこの映画はハリウッドの50年代の映画にオマージュを捧げているんですが、50年代というのは、戦争があってヨーロッパの監督達がユダヤ人であるなどの理由によって自分達の国で働けない、それでハリウッドに行って活躍するという時代だったわけです。そういう背景の中でハリウッドは黄金時代を迎え、そしてその黄金時代の映画というのは、非常に大衆を意識している映画であると共に、監督の深い世界観というのを描いていまして、そういう意味で映画としての質も高いと私は思っていまして、それでオマージュを贈るということなんです。それは具体的にはヒッチコックですとかダグラス・サーク、ビリー・ワイルダー、ヴィンセント・ミネリなどの作家に、オマージュを贈っているということです」
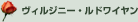
「私はこの役をこういう衣装で演じることは非常に面白く思いました。オゾン監督の作品というのは、過去の映画作品を随所にちりばめて、いろんな方へのオマージュを贈ったり、それから参照して引用したりしているわけなんですけれども、例えば私が演じたスゾンの役に関しては、オードリー・ヘップバーンのことをすごく重ねているわけです。私は着ている衣裳、これはディオールのワンピースなんですけれど、そのワンピースよりも髪の形や、それから帽子ですね、それらのほうがヘップバーンを思わせるものになっています。ま、実際には『麗しのサブリナ』とか『巴里のアメリカ人』を物理的にそのまま演じているわけではありません、あくまでもオマージュを贈るということで、そうした女優達にオマージュを贈るということ、そしてまたそういう女優達が来ていたような衣裳で演技をするということは、とても楽しいものでした」
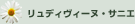
「確かに私の衣装や人物像を見ると、『巴里のアメリカ人』のレスリー・キャロンなどを思わせるものなのですが、ただ役柄としては本当にシンボリックにそう思わせているってだけで、それをそのままもってきてダンスをするって感じではありませんので、そういう意味ではかなり制限されたものだし、引用されていたとしても私はそんなに気にしないで演じました。衣装に関しては、8人の中で私だけズボンを履いていたので、非常に動きの自由がありましたし、男性的な役柄の要素を出していくことができたと思います」

ありがとうございました。
この後、映画に協賛もしている銀座LANCELのブティック(資生堂ビルのすぐ近所)に場所を移してささやかなカクテルパーティが開催され、もちろんオゾン監督やヴィルジニ−・ルドワイヤン、リュディヴィーヌ・サニエも参加。取材陣も押し寄せてパンク状態の中、シャンパンで乾杯。お三方は10分ほどで退場したのであった。
Text:梶浦秀麿
|